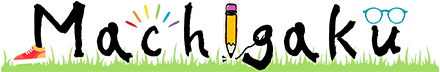【報告】なごみの始まりから「まちがく」の始まりを知る『NPO 法人なごみの 13 年』

第 1 章 はじめに
このレポートでは、8/21(木)になごみキャンパスで開催された「なごみの始まりからまちがくの始まりを知る『NPO 法人なごみの 13 年』」の授業のようすについて述べています。
私は昨年度からまちがくに参加しており、当キャンパスにも何度か足を運んできました。しかし、「なごみが今までどのような活動に注力していたのか?」といった話や「どのようにしてまちがくが誕生したのか?」といった話を確かにまだ聞いたことがないことから、それらを含めた話が聞ける機会だと思い、この授業に参加した経緯に至ります。
第 2 章 当日のようす
(1)参加者
大学生 2 名と社会人 8 名の計 10 名が参加していました。
☆大学生については、2 名ともなごみのインターン生で、生命環境学部に所属しており、こども食堂などの活動にも携わっている関西学院大学 1 回生の学生さんと、3 回生 美術史を学んでおり、パリ万博パビリオンの空間づくりを研究しており、また子どもの手伝いをするのが好きな大阪大学の 3 回生の学生さんが参加していました。
☆一方、社会人については、不登校の学生さんでも安心して通える居場所づくりを提供している受講生や、地域で生徒たちと学ぶことを目標に日々尽力し続けている通信制高校の職員さんをしている受講生、福祉職公務員の仕事をしている受講生などさまざまな場面で活躍している人たちが参加していました。

(2)当日の内容
1アレンジしりとり
以下の 2 つに気を付けながら、アレンジしりとりを 1 グループ 3 人~4 人でしました。
【A】 小さいモノから大きいモノへ
【B】 大きさをことばと合わせてジェスチャーをおこなう
みんなで楽しみながらアイスブレイクができていた印象がありました。アイスブレイクは、頭と心と体をほぐすものだとワーク終了後に話があり、実際やってみるとそのことがよくわかりました。

2田村校長の学生時代
講師の田村校長は、明石生まれで、現在では子ども3人のお父さんです。その彼の人生をここでは遡ることとしましょう。
彼は、関西学院高校・ 大学の出身で、社会福祉学科を卒業されました。当時男子校であった関西学院高校にスポーツ推薦で入学した彼は、中学でもやっていた剣道部を続けることとなりました。中学時代は土日遠征や長時間の活動に中学で剣道を辞めたいと思っていましたが、高校時代の部活の先生が「ケガがあってもやろう」と背中を押してくれたこともあり、続けたのち、そのまま大学に進学した経緯に至ります。大学の 4 年間については、以下の通りです。
≪1 回生≫ 将来のことを考えていなかったため、「何になりたい?」「どこに行く?」といった焦りが出てきました。そこで考えた校長は、学校のボランティアセンターに相談に行き、ボランティア活動や小中学校で行く自然学校などの指導補助員に参加していきました。部活動にも積極的に取り組んでいました。所属は「ハーモニカ部」で、リーダーをしていました。卒業するまで部長を努めたのち、部員が倍になって卒業することとなりました。
≪2 回生≫ 指導補助員として西宮だけでなく、明石や姫路にも出向いていた校長は、「子どもも先生方も窮屈なのではないか?」といった教育現場に違和感を感じるようになりました。「このままだとやばい」と感じた校長は、好きだった学校に疑問を抱くようになりました。
≪3 回生≫学校を変えたいといった考えが生まれてきました。しかし、教師にもなってもない人がその旨をどこかに伝えてもさすがに説得力がないので、大学生以下の人たちにも協力してもらいながら、自分で学校を作りました。詳しい詳細は以下の通りです。
団体名:学生団体Clover
場所:南山城村の廃校舎
期間:3泊4日
人数:小中学生併せて25名+大学生25名
予定:【春】団体結成→「子どもが本気で行きたくなる学校づくり」企画書作成→【夏】がっこうキャンププロジェクト
夏休みの終わりの時期開催し、この企画が終わり換算する大阪駅で、参加していた子たちは、また休み明けから始まる「学校」を楽しみに帰っていきました。
その姿を見て、企画したメンバーは「がっこう」を創ったと思っていたが、子どもたちにとっては非日常体験の場にすぎなかったことに気づかされたという。
ただ、企画したことに意味がなかったかというとそうではなく、子どもたちが普段通う学校とは別の場所に、非日常の体験や関わりができたことはかけがえのない刺激であり、この体験にこそ可能性や価値を感じたようです。
≪4 回生≫ Cloverの活動が新聞に掲載されるようになりました。自分自身が地域が求められているなど考えていませんでしたが、その依頼に答えるスタイルで、団体の活動を継続しました。
参加者の保護者の方たちともコミュニケーションを取りながら、活動を進めていきました。続けていくうちに、「もっと続けたい」といった想いが生まれたことがきっかけで、「NPO 法人なごみ」を起業することを決意。

3なごみ~誕生前~
キッザニア甲子園ができる前。リアルな職業体験(社会教育)をおこなったのがNPO法人くろーばーの最初の活動です。具体的にはさくら FM でのラジオ体験や車の整備体験などでした。
ちなみに、体験の費用については、グループ内で話し合った時は、「3 千円~ 8 千円なら出す!」といった意見が出ましたが、実際当時は1,500 円で開催していたようで、 NPO 負担でやっていたとのことなので、かなりの赤字であったに違いありません。
「まちの中で、誰もが学びたい時に、学べる環境が平等にある場所」を目指しながら、再スタートを図りました。
そこから「日常生活圏域の中で、非日常の体験ができることが理想」だと改めて感じ、地域に根ざした活動をおこなうこととなりました。その地域こそ、今も暮らしながら活動を行う「鳴尾東地域」だったのです。
当時からつながりがあった会長さんが多世代交流が可能な居場所を提供してださり、多くの学生さんや高齢者の方、障害のある方、自治会ないし育成会の方といった多岐に渡る形で地域を巻き込みながら活動を進めていく事になります。
疲弊した地域で、イベントや社会教育は生まれない。
「まずは地域をもう一回強く元気にしなくては」という固い決意から、まずは「地域づくり」中心の活動に軸を置くことに決め、2013 年NPO法人なごみが誕生しました。それが11 年前の話。

4なごみ~誕生後~
地域住民で構成された「なごみ」は、全ての世代が、暮らし続けられるまちを目指し今もなお活動しています。活動については多岐にわたっており、不登校支援やみんなで晩ごはんを食べる会といった内容となっています。関わっている人は400 人を越え、年配の方が多いとは言いながら、6 割が 50 歳以下がまちに関わり始めているというのです。さまざまなスタイルでおこなっているので、以下に取り上げることとします。
イベント型:マルシェ「ほっともっと」
[土日単発、作るモノを出す、大学生 高校生 主婦が対象]
貢献型:まちのよろずや
[不定期、活動費アリ、全世代が対象]
→高齢者に対して、高校生はスマホを教えたり、大学生は通院や買い物に同行したりしています。ちなみに、最年少登録者は 9 歳で、最年長は 93 歳とかなりの差があることがわかります。9 歳は犬の散歩に同行したり、植物の水やりをしたりと活発に動いているとわかりました。
参加者共創型:なごみで晩ご飯
[地域の弁当屋とコラボ、鍋やタッパーのみの持参で可、全世代が対象]
→参加者には 1 回につき 600 円をもらって活動していました。「高い!」といったトラブルにはなっていないのです。なぜなら、試食会を 3 回実施し、メニューやパッケージを参加者と話し合ったのち、当日のようすを想像しながら 1 時間半の模擬練習をしていたからです。また、地域の弁当屋とコラボしていた理由から、参加者はご飯を取り分けたり、テーブルを拭く程度で良かったので、早く来るも無かったというのです。
趣味型:高齢者によるコミュニティの場「tsumu」
[手作り、布記事を使ったハンドメイド商品づくり、オリンピックに出たい高齢者が対象]
紹介型:仲間を増やす
[A 自分が参加する→B 知り合いを紹介する ]
当事者活動型:まなびのサブスク「まちがく」
[のぞみを実現する場(やりたい 知りたい 聞いて欲しい)]
4状況整理(ペアワーク)


5田村校長が活動を続けていく上で大事にしていること
最後に、田村校長が活動を続けていく上で大事にしていることについてお話がありました。それは、以下の 5 項目です。
I、立場を変えることで、言語の違い 主義、主張を知る努力
II、自分自身は「主体的」であるかどうか?
III、声を聞き、声を聞いた後を大事に育て合う
IV、誰もが「何かしたい」と思った時に「何か」ができる環境と土壌づくり
V、自由に「学び合い」が生み出される地域
第 3 章 まとめ
私自身の感想
なごみが地域を元気に盛り上げようと暮らし続けるすべての住民を対象に晩ごはんの会を開いたりしていたと知りました。会話しながら楽しく交流できるような多くイベントが実施されていたというのもなごみの 1 つの強みだと捉えました。なごみの活動を知るだけでなく、「どのようにしてまちがくが誕生したのか?」といった問いに対して、「さまざまな活動が確立していく中で、のぞみを実現する場(やりたい 知りたい 聞いて欲しい)が不可欠であると知り、誕生した。」といった答えも知れて、非常に有意義な 1 時間半を過ごせました。
参加者の感想
グループワークで一緒になった 2 名の受講生から感想をいただきましたので、共有します。
→ボランティアは大変であると知りながらも、ヒトもまちも巻き込みながら活動していく田村校長の姿は素晴らしいと感じました。
→社協となごみはまちを巻き込む 1 つの場として重なっている部分があると知れたので、良かったです。
担当者:上田 朝陽(まちがくレポーター)